|
アスペルガー症候群とWittgenstein
(『精神科治療学』19-9)
福本 修
I.はじめに
小論は、1996年に筆者が『イマーゴ』に寄稿した、<「心の理論」仮説と『哲学探究』――アスペルガー症候群[から/を]見たウィトゲンシュタイン>4)という論考を受けて、特に成人例を中心とした今日の高機能自閉症の理解に寄与しようとするものである。ここでは、高機能自閉症/アスペルガー症候群(以下AS)および「心の理論」仮説の解説は省略して、Ludwig Wittgenstein(1889-1951)の哲学的思索がASひいては人間の心の経験構造を抉出していることを、より具体的に示すことを主眼としたい。
今回編集部からは、特にASと創造性の関連で彼を論じること5)が筆者に求められた。一般に、作品と作者・著述と著者を直結させて論じることには、単純化と還元の危険が伴う。殊に理論が考察の対象の場合、そもそも理論の眼目はそうした個人的偏倚を脱却した普遍性を主張するところにあるから、最も有意味な部分を捨象した残りを扱うことになりかねない。また、断片的な類似性を指摘するだけでは、系統だった吟味に耐えない主張に終わる。小論ではこうした問題を踏まえた上で、Wittgensteinの提示する例を、彼の思索と彼個人との繋がりの痕跡として読んでみる。彼がAS様態に親和的だったことにはほとんど疑いがないが、極限に至る追究の結果、あらゆる人間の心の働きに通底する構造を見出した。それは彼が比類なき天才であったためばかりでなく、ASの特性も関与していると思われる。
II.問題の所在――「規則に従う」ことに内在する困難
まず、彼が何を問題にし、それについてどう考えたのかを見る。一般に、彼は『論理哲学論考』17)(1918完成)では要素命題という言語の一般的構造の分析を通じて世界の構造を像として示そうとしたが、『哲学探究』18)(1953死後出版)に至って要素命題および真理関数論を超えてさまざまな言語活動に立ち返り、言語の意味を「言語ゲーム」における使用の規則として捉えるようになった、と言われる。意味が使用であるとは、言葉の意味の本質が指示対象に呼応した何らかの像や心的過程(語感)にではなくて、使い方自体にあるということである。そしてその使用の規則は、論理学のように厳密なものではなくてさまざまな「言語ゲーム」が「家族的類似性」を保つ緩やかな結びつきの中にあり、「生活形式」の一部とされる。これは一見、論理の精緻な追求を放棄して、日常世界の肯定に流れているように映る(それが彼と袂を分かったRussellによる批判である)。しかしそこには、厳しい推敲の連続があった。寡作家と思われていた彼は、死後に幾つもの著作が見出され、全部出版すれば更に50冊分以上の遺稿を書き溜めていた(重複も膨大と思われるが)。ここでは、中期の講義録1)からの一例を挙げる。訳者の解説12)を参照しつつ読むとしよう。
1934年秋の講義で、彼は「一般観念」(例えば植物)の意味をどう理解するかを主題とする。そしてそれが観念に随伴する心の中にあるイメージのようなものではなく、その語の「使用を知っている」ことに対応することを指摘する。子供が植物を持って来るように言われて何かを持って来るとき、植物の一般観念を参照しているとわれわれは考えがちだが、そうした見方は、その観念が「自然の事実」であるかのように原因を推測していて、「シンボル体系の規則」であることを見逃しているのである。種々の議論を経て彼は言う。
「[・・]40プラス20を数えるたびにいつも61を得ていたとしたら、われわれの算術は具合の悪いことになるだろう。これが真になるように算術を作ることもでき、そしてそうすることは、61と60は等しいと言うことではない。ある規則は、ものごとがいつもある仕方でふるまうと観察されてきたという理由で、選ばれるのである。
私が君に、「これが緑色だ」と言いながらある見本を与え、そして何か緑色のものを持って来るよう求めたとしよう。もし君が黄色いものを持って来て、私が、これは私の緑色の観念に一致しないと言ったとするならば、私は自然の事実を記述しているのだろうか。そうではない。黄色いものが緑色の見本に一致しないということは、一致についての規則を与えることなのである。黄色が緑色に一致しないということは緑色や黄色の本性上の何ごとかから帰結することではない。あるいはまた私は、緑色に一致しないものとは緑色と一緒にすると不快に見えるもののことであると言うこともできたのであり、そしてそのとき黄色は緑色と一致すると言われるかもしれないのである。あるものがある観念ないし考えに一致するとかしないとか言われるとしても、その一致不一致はわれわれが発見するものではない。一致とか不一致とか言われるものは、規則として定められるものなのである。そして規則は、役に立つか立たないかである。緑色や黄色が緑色の見本に一致するということは緑色の幾何学の一部であり、力学の一部ではない。すなわち、それは「緑色」の文法の一部なのであり、自然法則ではない」(強調は引用より)。
40+20が60でも61でもありうる、ということの意味は次に見るとして、「緑色」を指定したのに「黄色」を持って来ることがなぜありうるのだろうか。この場合、どちらにも色覚の異常がないことは前提であり、「緑色」の直示的定義として「色見本」を見せてさえいる。だから「黄色」を持って来た相手には、直ちに「それは違う」と言いたくなるだろう。それでも、相手は(こちらから見て)「黄色」のものを「緑色」のつもりで持って来ることが可能である。それはWittgensteinが言うように、「色の一致」で何を意味するかに関わる。例えば、「並べたときに不快感がない」というポイントが相手にとっては「同じ色」の意味であるならば、「これは緑色です」と「黄色いもの」を持って来ても、何ら矛盾はないのである。そこで当惑して、相手に「どういうつもり(=規則)なの?」と尋ねて初めて、不一致の由来が明らかになる可能性が生まれる。
「不快感」は、相手側独自の基準の一例に過ぎない。「色見本」の形や輝度ばかりでなく、見本の持ち方や見せ方が「緑色」を意味すると取られるかもしれない。つまり、色の物理学的特性が注意されるのは、色という言葉をそういう文脈で用いるという使用の規則が共有されているときのみである。極端に言えば、緑色を見たことがなくても、「これは緑色ではない」と言うことができる(それは、言語ゲームの規則次第である)1)。
では、「規則」は人々の間でどのように「定められた」のだろうか。それぞれを比較すると、ある規則を特に優位にする根拠は見当たらない。Wittgensteinは言っている。「[・・]私がある人に赤の見本を見せ、何か赤いものを持ってくるように頼んだとすれば、彼はそうするだろう。だが、必ずしもそうする必要はない。普通のことではないが、何か補色のものを持ってきてもよいのである。一つの使用が他の使用よりも直接的だというのではなく、ただ、その使用の方がより普通だというにすぎない」1)。日常生活では、通常特定の集団(例えば議会)が規則を定めてそれを広めたり、意識的に賛成して採用したりするというものではなく、習慣の積み重ねでいつとはなしに習得し、気がつくと合意しているといったものである。そこで問題となるのは、何が“普通”か不明瞭の場合である。
ここで次の例を引くことは、場違いではないと思われる。
杉山15)は、指導教官から女性に脅威を与えないよう警告されている理由が分からないという青年(言語性IQ=145)の相談に乗っていて、彼の思わぬ「認知の穴」に気づいたと言う。その青年は、痴漢に間違えられないように細心の注意をしているので、非難の理由が全く分からないでいる。彼は、親密でない人との間で許容される至近距離がどれくらいと思うかと尋ねられて、約30cmを示した。杉山は驚き、親しくてもその2倍、通常は1m程度離れていることが必要であると教えた上で、青年が想定した「規則」(という言い方はされていないが、結局そういうことである)の根拠を尋ねた。すると青年は、「義務教育から授業のときには、親しくない者でもその距離で机を並べている」ことを挙げた。
これが純粋に「認知」のみの問題で、青年の欲動や情緒と関係がないのかどうかは不明だが、彼の「規則」は、実践が或る範囲に収まっている限りでは適応的だった。一般にASがあっても、10才前後には「心の理論」の問題は通過すると言われる。しかし、それは通常の直感的に行なう仕方ではなく、おそらく複雑な推論・近似と補正を重ねて作り上げた産物である。その際自己流に、思い掛けない規則を生み出している可能性はつねに存在する。辞書的定義の外では、人々が場面に応じて規則を柔軟に運用しており、それと一致しない可能性の方がむしろ大きい。
Wittgensteinは、『探究』においてこの問題を次のように要約している。「これがわれわれのパラドックスであった――規則は行為の仕方を決定できない、なぜならば、どんな行為の仕方もその規則と一致するようにできるから。答えはこうであった――何でも規則と一致させることができるのならば、それは規則と一致しないようにもできるのだ。だから、ここには一致も不一致もないことになる」(第201節)。では、せめて論理学や数学では、こうした誤解や不一致がないのではないだろうか。しかし彼は、40+20が60でも61でもよいと書いていた。この奇妙な事態をより一般的に考察した「懐疑論」に移るとしよう。
III.Kripke-Wittgensteinの懐疑論
論理も計算も、記号を共有して一定の規則によって行なう行為である限り、上記の不一致の余地は、つねに存在する。本題に直ちに入るために、黒崎9)による例を取り上げる。
人は以下の数列を見て、その次の数を述べよと言われれば、10を正解とすることに異議を唱えないだろう。
2 4 6 8[ ]
その理由は、n番目の項目を定める規則としてf(n)=2nを想定しているからである。しかしながら、答えが0であると言い張ることも不可能ではない。それは式として例えば:
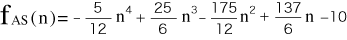
を思い描いていた場合である。そのとき、第4項までは一致しているが、n=5となると、fAS (5)=0である。当然ながら、これは偶数の数列の場合にのみ起こりうることではなく、あらゆる計算において生じることである。Kripke8)はこのことを、「プラス」と「クワス」という計算法の対照によって巧みに示した。ここで関わる点のみについて言うと、要は、有限個の実例から普遍的規則を一つに絞ることはできない、ということである。Kripkeはこれを、「最も根源的で独創的な懐疑的問題」と呼ぶ。と言うのも、従来の懐疑論がHumeを代表として、経験則の因果的必然性への批判だった(平俗な例を挙げれば、太陽が毎日東から昇り西に沈み続けてきたからと言って、明日もそうであるという保証はない)のに対して、ここでは論理的・数学的に真であるはずのものまで必然性を失うからである。
多くの人(非AS)にとっては、fAS (n)は冗談か極めて不自然な想定であり、こういう論理的可能性を完全に排除はしなくても、そこに自然数の数列を推測する方がよほど自然である。また、f(5)に一般的に期待される値が10であることにも、自然に合意するだろう。だがその理由を改めて問うと、なぜなのだろうか。ちなみに、fAS (n)に6・7を代入するとfAS(6)=−38、fAS(7)=−136となり、もはやf(n)=2nすなわち偶数の数列とは、似ても似つかないものになる。この式は全くの喩えに過ぎないのだが、部分的に一致していたのに突如大きく逸れる可能性があること、しかしそこにもASなりの一貫した規則が存在していることを示す点で、示唆的ではある。但し、このような“より自然な”規則に気づかないことは、障害の有無と関係なく起こりうる。それは、自己中心的な視点に固執した場合である。その一例は、天動説による天体の運行だろう。物理法則としては、地球をも含めて惑星がおしなべて楕円軌道にあると想定すれば遙かに単純な規則が得られるが、自分を外から見るというパースペクティヴの転換ができない間は、極めて複雑で容易に理解できない星の動きを受け入れなければならなかった。
このパラドックスは、Kripkeが初めてWittgensteinのテクストの中に見出した。彼はそれに対して「懐疑的解決」と呼ばれる解答を与えた。それについても極めて単純化して述べると、規則の一致が無根拠で一歩新たに進むたびにつねに「闇の中の跳躍」を行なっているにしても、それに実際の使用上何の不都合もなく、このパラドックスには意味がない、とするのである。そもそもほとんどの場合根拠を改めて提示せずに一致するし、不一致の場合も「計算間違い」として見解を一致させることができるからである。
実は正統的なWittgenstein解釈は、そもそもKripke8)に「誤読」があることを指摘している7)。つまり、この「パラドックス」はWittgensteinが賛成しているものではなく、彼の見解は、同じ第201節の第二段落以下、「ここに誤解があることは、以下のことから明らかである・・」にある。その主張によれば、規則に一致しているかどうか確認するために規則の背後に遡ろうとして解釈を繰り返すことは、「規則に従う」ための必要条件ではない。そうした解釈は余分な作業であり、人は既に、従うべき慣習を身に着けている。「規則に従う」ことは一つの実践である。その真偽の確認は、私的・内的にではなく、公的に他者と行なわれる。そこから、「私的に」規則に従うことはできない、という議論が続く。――こうしてKripkeの論法はWittgensteinに関しては退けられる。だがKripkeの解釈はあまりに独創的・生産的だったので、「Kripkensteinの懐疑論」7)とも言われる。
Wittgensteinの解法を、改めて見てみよう。彼が「私は根拠なしに行為する」(第211節)、「・・私は直ちに完全な確信を持って行為し、その行為には実は根拠がないということが私を悩ますことはない」(第212節)、「私が規則に従うとき、私は選択をしない。私は規則に盲目的に従うのである」(第219節)などと言うとき、彼は「因果的連関と論理的連関の差異」(第220節)を考えていた。この対比は、先の講義における「自然法則」と「シンボル体系の規則」のそれと同等である。後者の規則に、自然科学的な「原因」を求めることは、適切ではない。そこでできるのは「理由Grund」を問うことだが、それも、「規則がそうなっているから」というところで終了し、それ以上の根拠Grundはない。例えばf(n)=2nだからという説明は、その規則を選んだ理由(動機)の説明にはならない。むしろ、そう行為するように規則を習得したのである。また、行為の動機は、整合性(特定の数列という論理的連関)によって説明されない。だからと言って、行為に特定の規則を選択させる自然科学的な「原因」もない。それでも一致するのは、人は根本において、初めから共有しているものがあるからである。Wittgensteinは、「言語において人間は一致する。それは意見の一致ではなく、生活形式の一致である」(第241節)と述べる。その典型は、言語に加えて、他人に心があるという想定であろう。独我論や他我認識の問題として哲学的にはそれをどれほど洗練できたとしても、そうした疑問を持って議論しうること自体が、「生活形式」の基本的な一致を前提にしている。それが「普通」である。
規則に従うことの意味を論じたのに続いて彼は、いわゆる「私的言語」の不可能性を詳細に述べる。そこで重要なのは、やはり生活形式の一致である。彼は、哲学とは「蠅に蠅取り壺からの出口を示すこと」(第309節)だと言う。つまり、概念の混乱を整理して、擬似問題を解消することである。「私的言語」という考え方は、そうした擬似問題の一例である。では、そこまで重要な「生活形式」が一致しなければ、どういうことが起きるだろうか。あるいは、何が異なると、結果として生活形式が異なってくるだろうか。Wittgensteinがそのような問いを、哲学の一部として見なすかどうかは疑わしい。だが、奇妙な思考実験である「私的言語」とそれに続く「アスペクト盲」「意味盲」を含む彼のテクストは、そうした読みの余地を残している。
以下、哲学的には杜撰の謗りを免れないが、大まかな見取り図を素描したい。
IV.『哲学探究』18)が含む自閉的「生活形式」
私的言語論とは、以下のような議論である。「誰かが自分の内的経験−−自分の感じ、気分など−−を自分だけの用途のために書き付けたり、口に出したりできるような言語を考えることもできるのだろうか。[・・・]そのような言語に含まれる言葉は、それを話している者だけが知りうること、つまり、直接的で私的なそのものの感覚、を指し示すはずなのである。それ故、他人はこの言語を理解することができない」(第243節)。この定義に該当する「言語」は、一見ありふれていそうだが、実際にはそうではない。例えば独り言は、他者と共有する言語を用いている。ここで問題なのは、「私の内的経験を記述し、私だけが理解できるような言語」(第256節)である。彼は、「私」しか経験しない、痛みの感覚を取り上げる。痛みは、痛みという心の状態=対象が「私」の心の中にあって、それに「痛み」という名前が与えられているように見える。しかし「痛い」という表現は、痛みに対して泣くことしか知らなかった子供が身に付けた、新しい「痛みの振る舞い」である。つまり、「痛み」の状態が「痛い」として切り出されたのは「言語ゲーム」の一部としてであって、それは他人に理解できないどころか、むしろ他人から学んだのである。
では、自分の中の新たな感覚を対象として記述するときは、それが「私的言語」にならないだろうか。詳細は省くが、ここでもそれが言語であるためには、他者に了解されるだけの根拠づけBegru¨ndungを要する。そのためには主観的な印象ではなく、「基準」という「何か独立したところ」で確認されなければならない。さもなければ、彼の有名な比喩だが、「同じ朝刊を何部も買うようなもの」である。結局、「私的」の方に重きを置くと、それは「他人は誰も理解しないが、私は<理解しているように見える>音声」(第269節)となり、そのようなものは、通常の言語ゲームに参加していないのである。
ただ、Wittgensteinは「意味=使用」を強調するあまり、「内的過程」を全くそれに関与しないものとして削除する。理解・想像・想起・思考・・・のいずれでも、心的随伴現象は意味に何も寄与しない。彼は言う。「人が回すことはできても、それと一緒に他のものが動かないような車輪は、機械の一部ではない」(第271節)。また、或る人がチェスをするかどうかを知りたいときに、「彼の内部で起こっていることなど、われわれに全く興味がない」(vi)とも言う。確かに、他人の場合はそうだとしても、自分がする場合でもそうだろうか。随伴する経験の典型は、他人には見えない箱の中の甲虫に喩えられた「痛み」である。彼は、「甲虫」という語に一つの使用がありさえすれば、その中味が人によって異なっていても、絶えず変化していても、空でさえあってもよいか論じる(第293節)。これは各人が持つ痛みの経験自体を否定しているのではなくて、「痛み」の文法において、内的過程すなわち箱の中が意味に関係しないことを強調するものである。しかし、クオリア(qualia)すなわち主観的な質感は、意味経験に全く寄与しないのだろうか。むしろ、何が「普通」かを直感的に選択するのを、助けているのではないだろうか。
一方で、内的過程に印を与える“言語もどき”の私的な使用は、不可能ではない。Kripkeは、「自然な表現」を持たない感覚及び感覚言語が現に存在することを認める。但しそれは、共同体が既に感覚言語の規則をマスターしたと見なしうる人間による同定を、誠実な表明として尊重するからである。よってここでも、言語の習得が前提されている。「単なる命名が意義を持つためには、言語の中で既にたくさんのことが準備されていなければならない」18)(第257節)。では、本当に単なる命名にほぼ等しい内容しかない場合、どういうことになるだろうか。そのような“言語”は、出来事および対象と個別的に密着し過ぎていて、辛うじて自らの感覚を指示できるが、その時その場を超えて一貫したものを意味することはできない。そのため、規則性が相手に不明なばかりか、それを用いている当人にとっても、個物を超えた把握が困難なはずである。しかし臨床的に見られる記号の自閉的な使用は、それよりは当人の中で普遍性を持っている(Jessica Parkの例13))。ただ、特異なために他人には分からない点は変わらない。
Wittgensteinは、「語は対象の名前であり、文とはそのような名前の結合である」という言語観を否定した。それは彼が喝破したように、言語の自然な習得過程ではなくて、外国語あるいは未知の単語・表現を覚えるときの課程である。そこでは、一つの言語の習熟が既に前提にされている。この“誤解”は、彼が引用したAugustine 2)に認められる。しかしそれを再確認すると、以下のような糸口を含んでいることがわかる。「大人たちが何か或る物の名前を呼んで、それに向かうとき、私はその様子を見て、彼らがその物を指示しようと欲するときは、彼らは彼らが発する音声によってその物を言い表すのだ、ということを理解した。しかし私は、彼らのその意図を、すべての人々の生得言語である彼らの振る舞いから察知したのである。すべての人々の生得言語とは、彼らが何かを熱望する・保持する・拒否する・避けるとき、顔つきや目つき・手足の動き・声の調子などによってその心の状態を示す言語のことである」2)。「生得言語」とされる「振る舞い」は、「言語」と呼んでも「非言語」「前言語」と呼んでも、収まりの悪いものである。しかし確かなのは、これらの明言されていない副次的規則によって、それらを熟知さえしていれば、その場面で自然な「普通」の意味を、遥かに確定しやすくなることである。
それに対して「私的言語」は、こうした共有された文脈を欠く。その結果を、或る自閉症者は回顧している。「わたしは彼らの規則を尊重していないわけではなく、その場ごとに無数にある彼らの規則全てに、ついていくことができない・・・」16)。自閉症者が自分を異星人に喩えることが多いのは、「生活形式」がどうにも異なるからだと思われる。或るものをどう見るかという水準で、他の人々と食い違ってしまう。Donnaは言う。「あらゆる行為には二つの定義、二つの捉え方がある・・・彼らにとっての定義と、私にとっての定義だ」。
その基底にある構造的な問題について、Wittgensteinはやはり示唆を与えるように思われる。一つは、視点の転換の困難であり、もう一つは、自然な理解と内的実感が伴わずに規則に従うことの困難である。彼はそれぞれについて、「アスペクト盲」「意味盲」という概念を導入して考察する。
人が「アスペクト」に気づくのは、「或るものを見ている」状態から、それを「別のものとして見る」ときである。逆に、それまではただ何か「を見ている」ので、アスペクトは見過ごされる。有名な「兎-アヒル」の絵(Jastrow図形)は、兎の頭の絵としてもアヒルの頭の絵としても見ることができる。どちらの見方も直接的な知覚経験であって、点と線に解釈を加えた間接的な経験ではない。ここで彼は、奇妙な思考実験を行なう。「或る物を或る物として決して見ないような人たちのことを、われわれは思い描くことができるだろうか。この人たちには重要な感覚が欠けているのではないだろうか。あたかも彼らが色盲であったり、或いは絶対音感を欠いているかのように。われわれはこのような人たちを、とりあえず『形態盲』ないしは『アスペクト盲』と読んでおこう」(第478節)(xi)。

Jastrow図形
この障害を持つと、今まで或る物として見ているものを改めて別の物「として見る」ことは困難である。そのため、見ている物を固定的に(字義通り)受け取りがちであると同時に、他者から見たアスペクトを容易に想定できだろう。これは、その場に密着しすぎていて応用が利かない自閉症者たちの学習を思い起こさせる。アスペクトの問題は、より一般的に言えば、「振りpretence」や「ごっこ遊びmake-believe play」に関わる。「子供たちのゲーム:彼らは、例えば一つの箱が家だと言う。するとその結果、箱は隅々まで家と解釈される。ある思い付きが箱に織り込まれる。[・・]その場合、彼が箱を家として見ている、と言うこともまた正しいのではないだろうか」18)(xi)。つまり、「アスペクト盲」は「ごっこ遊び」の不能であり、「『心の理論』仮説」から見た自閉症の基本障害である。
「意味盲」とは、更に奇妙な設定である。その動機が、言語の意味にとって語の「意味経験」が不要なことを示すためであることは分かる。「私が<意味盲>という事例を想定したのは、言語を使用する際には意味の経験は重要性を持たないように思われるからであり、従って意味盲の人々は大したものを失うはずがないと思われるからである」 19)(第202節)。しかし彼はまた、そのような人々は「機械的に語っているような感じ」で、「われわれよりも生気に乏しい印象を与え、われわれよりも<ロボットのように>振る舞うに違いない」 19)(第198節)と言う。その理由は一つには、非言語的なコミュニケーションがすべて雑音扱いされるからである。それから、彼はこうも言う。「もしも意味が心に浮かぶことを夢になぞらえるなら、われわれは通常は夢を見ることなしに語る。<意味盲>の人はいかなるときも夢を見ることなしに語る人であると言えよう」 19)(第232節)。人は他人に夢を語る必要はないし、意識する必要もないが、全く夢を見ないとしたら別問題である。「意味盲」が失うのは、「夢」で指示された、私的で内的な経験の次元である。そうした経験がどのようなものなのか、彼は詳しく語らないが、意味盲の人は<ロボット>化し19)(第324節)、「心あるものの反対」となる。それは、人と人の間で慣習的に成り立っている、自然な情緒的交流の広大な領野からの疎外である。それでも彼が失うものは少ないと言うのは、彼が実際に他者理解に困難を抱えていたことの裏面だろうか。
V.おわりに――Wittgensteinその人
彼は、哲学者が普通の人たちの持たない疑問を提出するのは、洞察力があるからではなくて、或る意味で不足しているからだと言っている。 どの評伝10)も、彼が「風変わり」で「聞いている人を疲れさせる」一方的な人だったと述べている。少年時代から青年期のエピソードも含めて、生涯にわたる彼の奇妙さを拾い上げることは容易である4)6)。殊に、対人関係に関する逸話には事欠かない。むしろ不思議なのは、そうした障害がありながら他の追随を許さない独創性を発揮したことである。
一般に、自閉スペクトラムはその特徴を欠陥として捉えられる傾向がある。こだわりや自己中心性も多くの場面で問題を引き起こすものだが、事が科学的追求となると、その徹底性と完璧主義が、熱中性および常識の無視と相俟って、大きな成果をもたらしうる。哲学から一時撤退していた彼は、実家の建設に興味を持ち、途中から仕事に加わってそれを占領し、異様な精度を要求して大工たちを疲弊させた。最後には、出来上がった天井を3cm上げるよう指示して実行させた10)。これは、彼のバランス感覚が命じたのだった。姉はもちろん彼を全面的に支持した。彼のデザイン感覚は秀逸で、あるレセプションで彼が見かねてあるコートのボタンを二つ切り落とすと、それは遙かにエレガントに見えるようになったと言う。ちなみにそのコートは、エリザベス女王のものだった3)。彼は、作業がつねに精密なことでも知られていた。第二次大戦中、彼が薬剤師の助手として調合した皮膚科用の塗り薬は、最高の精度だった。但し別のエピソードによれば、彼は患者に「飲まない方がいい」と言いながら、薬を配っていたそうである。彼の意見と役割通りすべきことは、別なのだろう。正確さへの彼のこだわりは、死の直前にも見られる。死を迎えつつあるが誕生日になった彼に、身辺の世話をしている婦人がケーキを持ってきて、祝辞として「ご長寿をお祈りします」と述べた。するとWittgensteinは彼女の方に向き直って言った。「自分が今言ったことをきちんと考えて欲しいな」14)。(婦人は泣き出して、ケーキを落としてしまった。彼には相手を泣かせた理由がわかっただろうか。)
ASを持つ者は、人の心の理解という誰もが意識せずに超えている課題につまづく。Wittgensteinも例外ではない。しかし彼は、彼が有した根源的な困難を哲学的思索の中に引き受けて、<人間存在の基礎条件>を明らかにしたように見える。
文献
1) Ambrose A: Wittgenstein’s Lectures. Cambridge, 1932-1935. Basil Blackwell, 1979.アリス・アンブローズ編、野矢茂樹訳、Wittgensteinの講義。ケンブリッジ1932-1935年。剄草書房、1991年。
2) Augustine AS: Confessions. 山田晶訳、アウグスチヌス著:告白。中央公論社、1978.
3) Edmonds D, Eidinow J: Wittgenstein’s Poker: The Story of a Ten Minute Argument Between Two Great Philosophers. Faber and Faber, 2001.二木麻里訳:ポパーとWittgensteinのあいだで交わされた世上名高い10分間の大激論の謎。筑摩書房、2003.
4)福本修:「心の理論」仮説と『哲学探究』――アスペルガー症候群〔から/を〕見たウィトゲンシュタイン(特集 自閉症)、imago (青土社) 7(11) 1996.10 p144〜163
5) 福本修:Asperger症候群(高機能自閉症)の創造性、「臨床精神医学講座special issue第8巻:病跡学」、中山書店、2002.
6) Gillberg C: A guide to Asperger Syndrome. Cambridge UP, 2002.田中康雄監修・森田由美訳:アスペルガー症候群がわかる本。理解と対応のためのガイドブック、明石書店、2003.
7) 飯田隆:ウィトゲンシュタイン 言語の限界。講談社、1997.
8) Kripke S: Wittgenstein on Rules and Private Language--An Elementary Exposition, Basil Blackwell,Oxford,1981.黒崎宏訳:ウィトゲンシュタインのパラドックス、産業図書。
9) 黒崎宏:クリプキの『探究』解釈とウィトゲンシュタインの世界。現代思想、vol.13-14, pp.32-43, 青土社,1985.
10) Monk R: LUDWIG WITTGENSTEIN. The Duty of Genius, Jonathan Cape Ltd, London, 1990. ウィトゲンシュタイン 1・2、みすず書房。
11) 茂木健一郎:脳とクオリア――なぜ脳に心が生まれるのか。日経サイエンス社、1997.
12) 野矢茂樹:心と他者、勁草書房、1995.
13) Park, C::Autism into Art: A Handicap Transfigured. in Schopler, E., Messibov (Ed) High-Functionning Individuals with Autism. Plenum Press, New York & London, 1992.
14) Paxman, J: The English: A Portrait of a People. Penguin Books, 1999.小林章夫訳:前代未聞のイングランド。英国内の風変わりな人々。筑摩書房、2001.
15) 杉山登志郎(編著):アスペルガー症候群と高機能自閉症の理解とサポート。学習研究社、2002.
16) Williams D: NOBODY NOWHERE, London, New York, Toronto, Sydney, Auckland, Doubleday, 1992.河野万里子訳:自閉症だった私へ、新潮社。
17) Wittgenstein L: Tractatus Logico-Philosophicus, Tr. by Ogden CK. Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1981. 論理哲学論考、ウィトゲンシュタイン全集1、大修館書店。
18) Wittgenstein L: Philosophical Investigations. Tr. by Anscombe GEM, Basil Blackwell, 1958. 哲学探究、ウィトゲンシュタイン全集8、大修館書店。
19) Wittgenstein L: Bemerkungen uber die Philosophie der Psychologie, Basil Blackwell, 1.1980, 心理学の哲学、ウィトゲンシュタイン全集補巻1、大修館書店。
.

|

